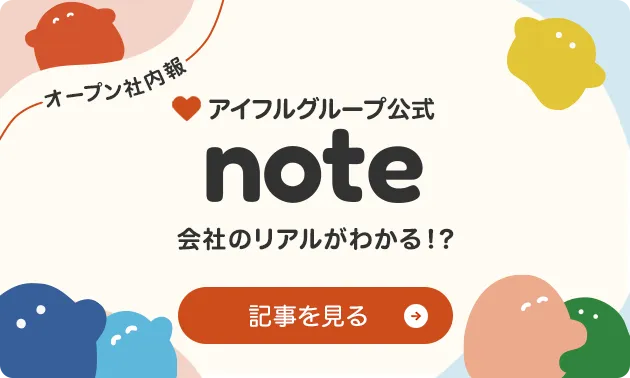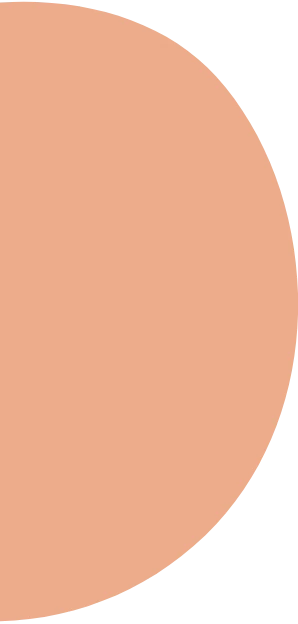

IT金融グループへ、変革の真っ最中。アイフルの看板部門を率いる部長の挑戦と、めざす未来

大学時代、サークルでイベント企画に邁進。人を動かすマネジメント力を養う
自らの幼いころを振り返る時、吉野の頬は緩みます。
「家でゲームをしたり、本を読んだりするインドア派でした。自分で言うのも恥ずかしいのですが、素直で明るく、そして調子に乗りやすいタイプでしたね。両家の初孫だったこともあって、ちやほやされて育ちました。息するだけで偉い、みたいな(笑)」
周囲の愛をたっぷり受けて、すくすく育った吉野。大学では理学部で数的理論を学ぶ一方、サークル活動に熱中しました。このころ、今に通じる「マネジメント力」を養うことになります。
「手話サークルに入りました。新入生歓迎コンパに参加して、そのまま入部届を書いたような流れでしたね。仲の良かったサークルの会長に『君に任せるから、メンバー同士の交流イベントなどを好きにやってほしい』と言われ、頼りにされていると意気に感じた私は、定期的な飲み会や学祭での出店、合宿などの企画に力を注ぎました。
前に出るのは好きじゃないので、自分が企画し、周りのメンバーに動いてもらうような形で進めていたんです。人に何かをお願いする場合には、目的や背景、注意点などについてきちんと説明し、相手にもよく理解した上で気持ちよく動いてもらうように心がけていましたね」
サークルという組織の中で、人を上手に動かすすべを学んできた吉野。新卒で選んだ会社がアイフルでした。
「父が金融業界で働いていたので、この業界は選択肢のひとつでした。中でもアイフルはテレビでCMがよく流れていて、勢いのある会社だと感じましたね。一定のリスクを取って、それをうまくコントロールしながら高い収益性を実現するという会社のビジネスモデルも、私の好みでした。
その一方で、結婚を考えていた私にとっては上場会社で安定的に給料を得られることや、カレンダー通りに土日祝日に休めるというワークライフバランスの充実も魅力だったんです」
2005年に入社し、店頭営業でキャリアをスタートさせました。法人管理部、マーケティング部などを経て2018年、デジタル推進部の立ち上げメンバーに選ばれたのです。

4人で始まったデジタル部門。「UI/UXなら特色を出せる」とシステム内製化に挑む
デジタル推進部は吉野を含め、わずか4人での船出でした。
「社会でIT化が急速に進む中、当社も時代の変化に対応すべく部を立ち上げました。どのような業務をメインに進めていくかを考えるところからのスタートです。
金融業は他社との差別化を図るのが難しい分野ではありますが、部署の立ち上げからおよそ1年後、システムを内製化し、UI(アプリ画面のデザイン)やUX(顧客体験)をスピーディーに開発できれば特色を出せると考えたのです。エンドユーザーが関わるWebサービスやスマートフォンアプリについて、それまで外注していたのを社内で開発するようになりました」
徐々に規模を広げてきたデジタル推進部は2023年に分割され、当時課長であった吉野はデジタル推進2部の部長に就任。現在では約50人のエンジニアらを束ねています。
「当部署ではよりお客さまのニーズに沿ったサービスの提供をめざし、引き続きアプリやWebシステムの開発の内製化を促進。同時に作業のスピードアップや開発品質の向上、コスト最適化を図っています。一方で部署を統括する私としては、アジャイル開発体制の拡充や、ユーザー部門との伴走型開発の導入・整備に力を注いでいます」
目を引くのが、離職率の低さです。デジタル推進1部、2部を通じて毎年0%~1桁%にとどまり、部員向けの定期アンケートでも一定の満足度を保っています。
「採用面接ではスキルだけでなく、企業カルチャーとのマッチングを大切にしています。入社したら一緒に働くことになる社員が同席し、候補者と価値観や実務について話し合って互いに理解を深めます。普段の業務では5~10分の朝会を設け、私から経営層の方針を含めてさまざまなメッセージを発信して一体感を醸成します。今後は新卒者の配属や、リスキリング目的の社内異動が増えることを踏まえ、エンジニアスキルの定点観測指標の導入や教育専門部隊の設置を予定。これまでOJT、個の教育が主でしたが、組織拡大に伴い体系的な教育部隊が必要と考えています」

スピード感を意識し、スマホアプリの更新に尽力。アプリ評価が急上昇して大きな自信に
手探りながらも、IT事業で着実に階段を上ってきたアイフル。その歩みを振り返る時、吉野は最初に内製化した製品、スマホアプリで「高い評価を受けた時の喜びは忘れられない」とうなずきます。
「外注先に出向き、各種契約内容の引き継ぎなどを経てアプリ開発を内製化しました。
当社が初めてエンジニアとして迎えた社員たちと手を携え、少人数ながらもスピード感を持ったアジャイル開発で、企画部門、デザイン部門と共にUI/UXの向上、機能追加や修正を繰り返しました。
内製化したことで、短期間でユーザーの意見を反映させながらアップデートを重ねられ、外注時代は2.6だったアプリ評価がトップクラスの4.7にまで上昇したのです。
衝撃的でしたね。使いやすさを評価する声が多く届き、私としても大きな手応えを得た瞬間でした。
この時に想像力、仮説思考の大切さを実感したのです。お客さまの立場になって『こんな開発、こんな改善をしたらもっと使いやすくなるのでは』とあれこれ考えを巡らせた上で実行に移すと、お客さまから反応が返ってくる。この繰り返しで改善していくことの大切さを、試行錯誤を経て学びました」
一方で、教訓として今も胸に刻んでいる体験もあるといいます。スマホアプリのプッシュ通知機能のテストをする際、開発メンバーが本番環境で実施してしまったのです。
「お客さまからのアクセスが集中し、Webシステムが一時的にスローダウンしました。その時、われわれのような金融業はお客さまの生活やビジネスに直結するサービスを扱っており、使えなくなると非常に困るのだと痛感させられました。今後はダブルチェックをしたり、自動化して人によるミスを排除したりと策を講じた上で、『当たり前に使える』という環境を整えなければならない。当時課長としてその重要性を大いに学び、反省した一件でした」
失敗を決して無駄にしない──。この体験を糧としていっそう成長することを、吉野は心に誓いました。

「お客さまから選ばれるプロダクト」を育てられる開発チームに。情熱を胸に誓う
IT分野で今、大きく羽ばたこうとしているアイフル。吉野は部署の未来像をこう思い描いています。
「将来的にはIT人材の割合を全社員の25%にまで引き上げるのが、当社の方針です。今後も開発チームを増員していく予定ですが、単なる規模拡大に終わってはいけません。『お客さまから選ばれるプロダクト』を育てられる開発チームに進化させていきたいと考えています。
われわれの仕事は、受託開発のような『指示をいただいて作って終わり』というものではありません。手がけるシステムの向こう側にはわれわれの提供するサービスがあり、さらにその先には多くのエンドユーザーがいらっしゃいます。お客さまが実際に使うシーンを想像しながら、工夫を凝らして提案し、プロダクトに反映させる。そのように、ビジネスに大きく貢献できる開発集団となることをめざしていきます」
IT集団としての発展を考える上で、吉野が重視しているのは「個人より組織単位でパフォーマンスを最大化させること」です。
「システム開発などの内製化をスピーディーに進められているのは、意思決定の早い独立系の当社ならではの強みです。金融業として歴史を紡いできた会社が変化を遂げている真っただ中で、こうしてチャレンジを続けられていることを誇りに思っています。
そのような当社にあって、組織の誰か、仮に私がいなくなったとしても自走していける集団になるのが究極の理想です。私ひとりだけがパフォーマンスを上げ、何かを動かしていくのではなく、みんなが動ける組織や制度を築き上げた上で、チームとして高い意識を持って成長していく。メンバー全員が今、さらなる飛躍をめざして一致団結しています」
当社がめざすのは、「金融業も手がけるテックカンパニー」。黎明期からデジタル部門を支え続ける吉野は、これからも変わらぬ情熱を胸に走り続けます。
 ピックアップ記事
ピックアップ記事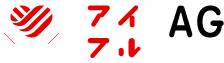
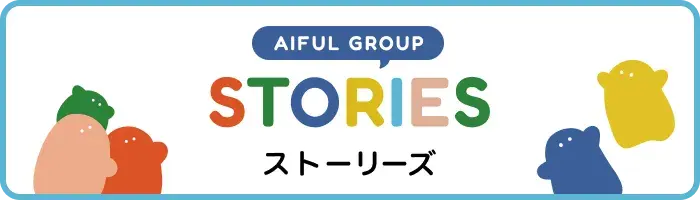




 STORIES一覧
STORIES一覧